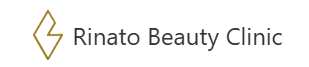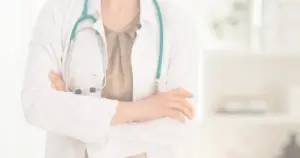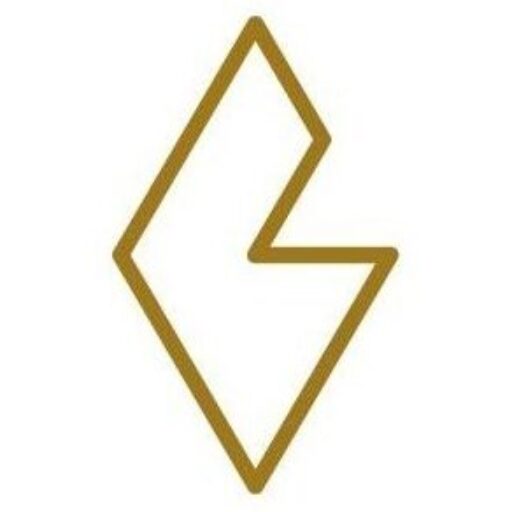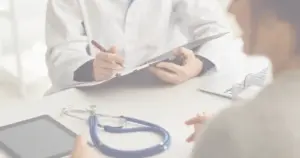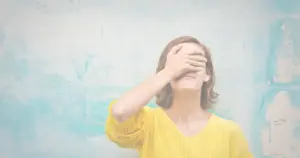糸リフトのダウンタイムは痛みや腫れ、内出血が1〜2週間程度続くことが多いです。比較的ダウンタイムが軽いといわれている施術ですが、症状の程度は個人差があります。
ダウンタイムの過ごし方を知らないと、症状が長引いたり悪化したりするリスクがあります。
そこで、本記事では糸リフトのダウンタイムの経過から過ごし方まで具体的に解説します。糸リフトの術後について詳しく知ってから施術を受けたい方は、ぜひ参考にしてください。
糸リフト(スレッドリフト)のダウンタイムの症状
糸リフトの主なダウンタイムの症状は、次のとおりです。
- 痛み
- 腫れやむくみ
- 内出血
- 引っ張られるような感覚
- 凹みやボコボコ感
まずは、よくある糸リフトのダウンタイムの症状や程度について詳しく解説します。
ダウンタイムの主な症状
糸リフトのダウンタイム中は痛みや腫れ、内出血に加えて、突っ張り感やボコボコ感を感じることがあります。
糸が馴染むまでは、異物が入っている感覚を強く感じやすいです。
痛み
糸リフト後は、糸が触れている部分に痛みを感じやすいです。また、糸を挿入した入口のこめかみ部分がじんじんと痛むこともあります。
施術中は痛みがほとんどありませんが、麻酔が切れると急に強い痛みを感じる場合があります。
痛みは、施術翌日から3日目まで感じやすいですが、内出血や腫れとともになくなることが多いです。
腫れやむくみ
腫れやむくみが出るのも糸リフトのよくあるダウンタイムの症状です。
むくみは麻酔が原因で起きるため、施術翌日から2日目くらいで良くなることがほとんどです。
腫れは糸が肌に入ったことによる刺激で起きます。腫れは強く出ることもあり、施術3〜4日後に治まることが多いです。
内出血
糸リフトの施術から数日経つと、内出血が出ることがあります。これは、ハリや糸を皮膚に入れた際に血管が傷つくことで起こります。
内出血が起きる場所は個人差があるため、人によっては目立つ場合も。
治るまでにやや時間がかかるため、術後1〜2週間程度で治まることが多いです。
引っ張られるような感覚
糸リフトの施術後は、糸が馴染むまで突っ張り感や皮膚が引っ張られるような感覚を感じることがあります。
これは糸リフト特有のダウンタイムの症状です。特に、笑ったときや口を動かしたときに感じることがあります。
数日から1週間程度で良くなることが多いですが、完全に違和感がなくなるまでは1ヶ月ほどかかることもあります。
凹みやボコボコ感
糸リフトが馴染むまでは、肌に触れたときに凹みやボコボコ感を感じるのもダウンタイムの症状の1つです。
糸リフトの糸には、肌を引き上げるためにトゲのようなものがついています。糸が完全に肌に馴染むまでは、このトゲのボコボコ感を感じることがあります。
引っ張られるような感覚と同様、1週間程度で良くなり、1ヶ月ほどで今まで通りの肌に戻ることが多いです。
ダウンタイムはつらい?症状の程度
糸リフトのダウンタイムは通常1〜2週間ほどで良くなり、症状も軽いことが多いです。
しかし、人によっては強い痛みや腫れを感じることがあります。軽いと思っていたら、想像以上につらかったと感じる人もいるようです。
また、使用する糸や引き上げの程度によってもダウンタイムの症状の程度が変わります。医師の技術力や個人の体質などでつらさが違います。
糸リフト(スレッドリフト)のダウンタイムの経過
糸リフト後の基本的な経過は、次のとおりです。
| 術後日数 | 経過 |
| 施術直後 | ・腫れやむくみ、痛みを感じる・引っ張られるような感覚が強く出る |
| 施術翌日~3日目 | ・むくみが消える・腫れや痛みのピークを迎える・内出血が出始める |
| 3日~1週間 | ・ほとんどの症状が軽くなる・内出血も薄くなる・突っ張り感やボコボコ感は残る |
| 1~2週間 | ・違和感も消えてダウンタイムの症状が治まる・効果を感じやすくなる |
| 3週間目以降 | 自然な状態となり完成 |
術後日数別に、糸リフトの経過を詳しく紹介します。
施術直後
施術直後は、麻酔の影響で痛みとむくみが最も強く出やすい時期です。
糸が一番馴染んでいない時期のため、引っ張られる感覚や触れるとボコボコする感覚など違和感を感じやすいのもこのタイミングです。
また、腫れも少しずつ出てきます。
施術翌日から3日目
施術翌日には、麻酔が抜けてむくみが取れてきます。しかし、痛みや腫れが強くなってくるため、施術翌日から3日目までがダウンタイムのピークです。
2〜3日目には内出血が出ることも多くあります。
この時期のダウンタイムの症状が最もつらいと感じやすいです。
3日~1週間
この時期はダウンタイムがピークを迎え、段々と症状が軽くなります。痛みや腫れはほとんどなくなり、内出血も薄くなります。
ただし、糸はまだ完全には馴染んでいないため、違和感は残っている状態です。
1~2週間
施術から1〜2週間経つと内出血や違和感もなくなり、リフトアップなど糸リフトの効果を感じやすくなります。
人によっては内出血や若干の痛みが残っている場合もありますが、ほとんどの場合はいつも通りの状態に戻ります。
3週間目以降
3週間から1ヶ月ほどで、糸が馴染んで違和感が完全になくなることが多いです。また、この時期に糸リフトに満足する人が多く、施術の効果を最も感じられます。
この時期になっても強いダウンタイムの症状がある方は、一度クリニックを受診することをおすすめします。
糸リフト(スレッドリフト)のダウンタイムの過ごし方
糸リフトのダウンタイム中は、次のような注意点があります。
- 運動など血流が良くなる行動は避ける
- 腫れがひどいときは冷やす
- 口を大きく開けない
- 硬いものを食べない
- 顔のマッサージや歯科治療を避ける
- 患部には触らない
- 仰向けで寝る
糸リフトのダウンタイム中の過ごし方を紹介するので、術後のイメージができない方は必見です。
運動など血流が良くなる行動は避ける
糸リフト以外の施術でもそうですが、血行を促進すると、腫れや痛みが悪化するので避けましょう。
特に、次のような行動は1週間程度は控えるのがおすすめです。
- 激しい運動
- 長時間の熱いお湯の入浴
- サウナ
- 飲酒
体を激しく動かしたり長時間熱いお湯に浸かったりすると、血流が良くなって腫れや痛みが強くなります。
また、サウナや飲酒もあっかの原因になるので控えましょう。
腫れがひどいときは冷やす
糸リフトの術後の腫れがひどいときは、患部を冷やすのがおすすめです。タオルに包んだ保冷剤を当てることで、腫れだけでなく内出血の症状も軽くなることがあります。
ただし、冷やしすぎは凍傷のリスクもあるので、様子を見ながら保冷剤を当てることが大切です。
口を大きく開けない
ダウンタイムが落ち着くまでの1〜2週間は、口を大きく開けずに過ごすことが大切です。
口を大きく開けると、糸がずれたり外れたりするだけでなく、違和感も強くなってしまいます。
糸が馴染むまでは口をあまり動かさずに過ごしましょう。
硬いものを食べない
口を大きく開ける動作と同じく、何度も噛むのも糸がずれる原因になるため注意が必要です。
特に、術後1〜2週間程度は次のような柔らかい食べ物を食べるのがおすすめです。
- 豆腐
- ゼリーやプリン
- おかゆ
- スープ
- うどん
また、水分が足りないと、腫れが悪化することがあるので、水分補給もしっかりしましょう。
顔のマッサージや歯科治療を避ける
顔のマッサージや歯科治療で大きく口を開ける行為も、糸がずれたり外れたりする原因になります。顔のマッサージは自分で行うのもよくありません。
どちらも糸が馴染む1ヶ月程度は、控えることが大切です。
患部には触らない
マッサージに限らず、スキンケアなど日常生活で顔を触らないように気を付けましょう。
肌に馴染むまでは糸が動きやすく、糸が動いてしまうと思ったような効果を感じられないことがあります。
また、ダウンタイム中は肌が敏感な状態のため、触ると痛みや腫れが悪化するリスクも高まります。
仰向けで寝る
顔を圧迫しないためにも、術後最低3日間は仰向けで寝るのがおすすめです。
横向きやうつ伏せで寝ると、患部が圧迫されて糸がずれたり顔に負担がかかったりします。
また、寝るときは高さのある枕を使うことで、顔への血流を抑えて腫れや赤みを軽減できます。
糸リフト(スレッドリフト)のダウンタイムが長引く理由
糸リフトのダウンタイムが長引く理由は、術後の過ごし方以外に次の3つがあります。
- 糸の引き上げが強い
- ポリプロピレンの糸を使用した
- 個人の体質
施術方法や糸の種類など、糸リフトでダウンタイムが長引く理由を解説します。
糸の引き上げが強い
医師が施術の際に強く引き上げると、その分ダウンタイムが長引くことがあります。
強く引き上げる際は、肌が不自然に持ち上げられることもあり、糸のトゲが皮膚を強く傷つけるリスクが上がります。
そのため、リフトアップ効果のみを求めて無理やり強く引き上げると、ダウンタイムの症状が強く出るため注意が必要です。
糸の引き上げる程度は医師とよく相談し、ダウンタイムや自然な仕上がりなどを意識して選びましょう。
ポリプロピレンの糸を使用した
糸リフトで使用する糸はさまざまありますが、ポリプロピレンを使用したいとの施術は、ダウンタイムが長引く可能性があります。
ポリプロピレンの糸は体内で吸収されないタイプのため、効果が持続しやすいのがメリットです。
しかし、その分違和感が生じやすく、ボコボコ感や凹み、突っ張り感などが長く続くリスクがあります。
個人の体質
糸リフトのダウンタイムの程度は、個人の体質によっても大きく変わります。
どのような体質の人が長引くかは定かではありませんが、人によってダウンタイムの程度や長さが違います。
体質の問題は治せないため、医師と相談して術後の過ごし方や糸の選び方を工夫し、少しでもダウンタイムを軽減するようにしましょう。
糸リフト(スレッドリフト)のダウンタイムを短くするポイント
糸リフトのダウンタイムを短くするポイントは、主に次の3つです。
- 医師やクリニック選びに気を付ける
- 糸の質をチェックする
- 挿入する糸を増やし過ぎない
糸リフトは術後の過ごし方だけでなく、施術前の時点でダウンタイムを短くする対策ができます。
少しでもダウンタイムを軽くしたい方はチェックしておきましょう。
医師やクリニック選びに気を付ける
医師の技術力が低いと、強く引き上げすぎたり違和感が出やすい位置に糸を挿入したりするため、注意が必要です。
糸リフトの経験が多いクリニックや実績の豊富な医師を選ぶことで、自然な仕上がりかつダウンタイムの短い施術を受けられます。
また、事前のカウンセリングでは、施術方法やダウンタイムについてしっかり説明をしてもらえるかチェックするのもおすすめです。
糸の質をチェックする
糸リフトは、糸の品質が悪いとダウンタイムが長引くだけでなく、思ったような効果が出ないことがあります。
糸リフトで使用する糸は非常に種類が多く、中には安くて質が悪いものもあります。
くりクリニックの公式サイトやカウンセリングで、糸の種類についてもしっかり調べておくことが大切です。
質のいい糸を選べば、最初から違和感が少なく、肌にもなじみやすいです。
糸リフトの糸の種類に関してはこちらの記事で詳しく紹介しています。
挿入する糸を増やし過ぎない
挿入する糸が多すぎると、その分ダウンタイムが長くなります。反対に挿入する糸の本数が少なければ違和感が少なく、肌への刺激も抑えられます。
クリニックでは1本ごとに料金が決まっているケースも多く、多い本数を勧めてくる場合も。
自分に本当に必要な本数を勧めるクリニックを選ぶほか、ダウンタイムに対する不安を伝えることで、最低限の本数にしてもらうようにしましょう。
糸リフトの糸の本数に関してはこちらの記事で詳しく紹介しています。
糸リフト(スレッドリフト)のダウンタイムに関するよくある質問
ここからは、糸リフトのダウンタイムに関するよくある質問を紹介します。
ダウンタイム中の疑問を解消してから、糸リフトの施術を受けてくださいね。
糸リフト後はいつから性行為ができる?
性行為は、糸リフト後1ヶ月程度は控えましょう。
性行為による摩擦や動きによって糸がずれることがあるため、マッサージや歯科治療と同じように1ヶ月程度は避けるのがおすすめです。
糸リフトで自然に笑えるようになるのはいつから?
術後1〜2週間ほどで自然に笑えるようになることが多いです。
ダウンタイム中は違和感がありますが、1〜2週間程度経てば笑ったときのひきつり感はなくなります。
ダウンタイム中はヘアカラーやパーマはできる?
ヘアカラーやパーマは挿入部分のこめかみの傷口にしみるため、術後1ヶ月程度は控えるのがおすすめです。
美容院だけでなく、自分でカラーする場合も1ヶ月ほどは我慢しましょう。
シャンプーはしてもいい?
シャンプーは施術当日からできますが、しみる場合は2〜3日ほど様子を見るのがおすすめです。
シャンプーは、こめかみ付近を強くこすらなければ問題ないことが多いですが、人によっては刺激を感じることがあります。
糸リフト(スレッドリフト)のダウンタイムが気になるならリナートビューティークリニックで相談を
糸リフトのダウンタイムについて相談するなら、リナートビューティークリニックの無料相談がおすすめです。
リナートビューティークリニックでは、効果や持続性、コストパフォーマンスにこだわった糸リフトを行っています。
治療後のアフターフォローにもこだわっており、糸リフトのダウンタイムに関しても医師や看護師がケアしてくれます。
まずは、リナートビューティークリニックの無料相談で糸リフトのダウンタイムの不安を解消しましょう。